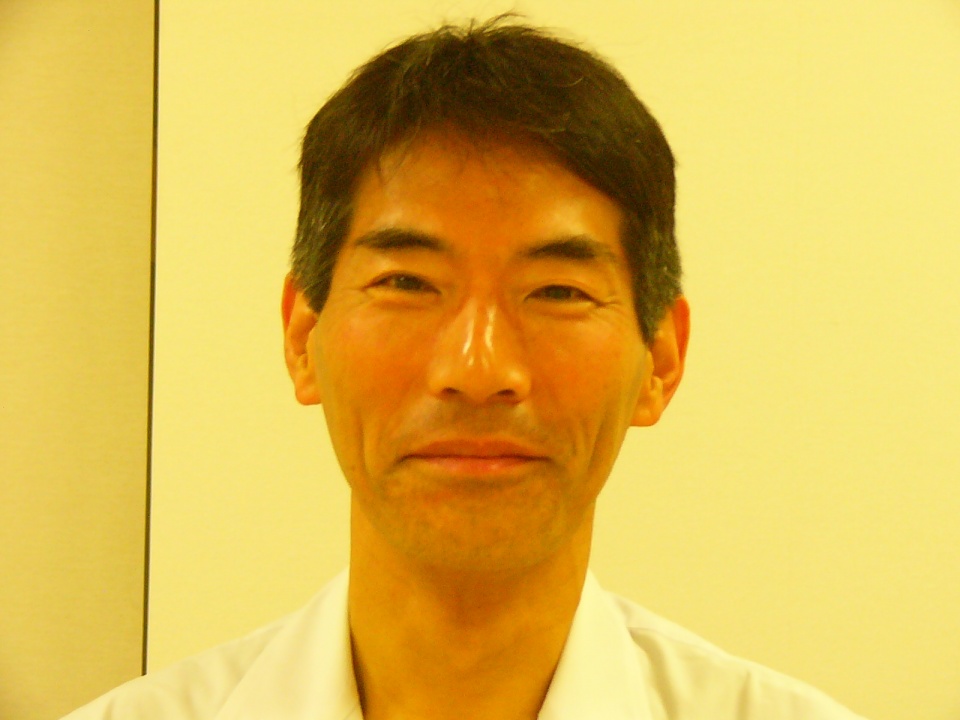「関西師友」12月号~1月号
人間の体は天の入れ物に過ぎない
「人は死なない!」 矢作直樹東大病院救急部教授の見解
神渡良平
肉体は魂の入れ物で、天が住まわれる器だ
古来から「寸鉄、人を刺す」と言う。短い条文ながら、みごとに宇宙と人間の本質をついているという意味だ。『言志四録』はそういう短い条文が多いのだが、ここはめずらしく長い。しかしながら佐藤一斎の人間観が語り尽くされている。他の条文はここから派生したに過ぎないとまで言うことができる。
闇室に独り静坐して、物事の本質を見極めようとして瞑想すると、次第しだいに見えてくるものがある。佐藤一斎はそのことを『言志録』第一三七条にこう書いた。
「吾が性は即ち天なり。軀殻は則ち天を蔵するの室なり。精気の物と為るや、天此の室に寓せしめ、遊魂の変を為すや。天此の室より離れしむ。死の後は即ち生の前、生の前は即ち死の後にして、而して吾が性の性たる所以の者は、恒に死生の外に在り。吾れ何ぞ焉れを畏れむ。」
(人間の本性は天が与えたものであり、この身体は天の与えた本性をしまっておく室である。精気が凝って形あるものとなると、天はこの室に寄寓し、魂が遊離すると、天はこの室より離れる。死ねば生まれ、生まれると死ぬものであって、本性の本性たる所以のものは、つねに死生の外にあるのだから、私は死を少しも畏れない)
なぜ、生に固執しないのか。佐藤一斎は淡々と説く。
「肉体は魂の入れ物で合って、天がそこに寄寓しているから生きている。天が離れたら、魂も遊離し、死が訪れる。天意を実現しようとして生きている私は、天意があるかぎり、一生懸命働くが、天が〝事終わりぬ〟と言えば、それに従うまでだ。だから私は死を少しも畏れない」
実にあっけらかんとした死生観だ。何ものにも執着していない。すべての存在の背後には天というものがあり、自分はそれに全面的に依存した存在だと思っているから、これほどに動じないのだ。
この佐藤一斎の死生観に接して、私は東京大学附属病院救急部・集中治療部部長を務める矢作直樹教授のことを思いだした。矢作教授は平成二十三年(二〇一一)八月、『人は死なない ある臨床医による摂理と霊性をめぐる思索』(バジリコ)がベストセラーになったことから、一躍世に知られるようになった。それまでも何冊かの専門書を出しておられたが、生と死に直面した患者を多く扱う臨床医として、真っ正面から死後の世界や霊の存在に対峙されたので、爆発的に読まれたのだと思う。
現代医学には検証不可能なものは扱わないという不文律があるが、矢作教授はいくつかの例を取り上げて、「魂は死なないのではないか」と投げかけた。器質的なものにあまりにも依存し、霊の存在を認めなかった現代医学に対する率直な疑問が、現役の東大医学部の臨床医から投げかけられたので、衝撃が大きかったのではなかろうか。
事実は事実として謙虚に受け止めよう
メールや手紙で寄せられた反響には次のようなものが多かった。
「私は小さい頃からうすうす死後の世界はあるのではと感じていました。というのは、私自身、霊の存在が見えたり、これから何が起きるかなど、未来が予測できたりしていました。でも母に、それを口外することを止められていました。おかしな子と見られるからというのです。
でも矢作先生の本を読んでみて、死後の世界って昔から語られており、特別なことではないのだと確信しました。私の直感をもっと信じていいんだと安心しました」
矢作教授は、私たちの先人は死や霊のことや死後のことを知っていて、ごく普通のこととして受け止めていたと書いているが、それに納得する人は多かったようだ。
矢作教授は霊にとりつかれて十階建てのマンションから飛び降り、救急外来に搬送されてきた二十代の女性Bさんのケースを紹介している。Bさんは他の霊に入り込まれて、無意識のうちに危険なことをしてしまうので、夫は危ないと判断し、マンションから実家に移り住んだ。ところがBさんは霊に入り込まれ、元住んでいたマンションから飛び降りた。
しかし、半身が植え込みに落ちたため、即死をまぬがれた。暗くて冷たい海の底のような所にいると、「あなたはここへ来るべきではない」と言われ、急に光が見えて目が覚めたという。
矢作教授は霊に入り込まれたときのBさんの険悪な表情と、意識が戻ったときの清明な表情のギャップに、これは憑依現象(悪霊にとりつかれる現象)だと思ったという。
続いて矢作教授は、会社を形成している五十歳代の男性Cさんの、二十八年前の明け方五時ごろ起きた交通事故を紹介した。助手席には六歳下の妹さんが乗っている。雨上がりの濡れた路面でスリップしてしまい、車が空中に飛んだ。はっと気がつくと、Cさんはなぎ倒された電柱に巻き付いて大破した車の左後ろ十メートル上から、妹さんと二人で見下ろしていた。
しばらくすると妹さんが、突然「お兄ちゃんは戻りなよ」と言い、その瞬間、車の運転席に横たわった状態で目が覚めた。妹さんはCさんの左肩に頭をのせたまま息を引き取るところだった。
救急隊員が駆けつけ、二人のバイタルサインをチェックし始めたが、思わずCさんは「妹はもう死んでいるんだ」と叫んだという。
また小学校三年生のとき、当時神奈川県の辻堂に住んでいて、父と江の島に自転車で行った帰り、自動車にはね飛ばれ、空中に舞い、頭から地面に落ちた。跳ねられた瞬間から意識は消え、病院のベッドの上で意識が回復した。かろうじて命は取り留めたものの、医者は外傷性てんかんのため、小学校卒業はできないかもしれないと母に伝えた。
この臨死体験と、そこで得た不思議な力は、矢作さんのその後の人生を大きく変えた。「なぜかはわからないけれども、すべてがわかってしまう力」を得てしまったのだ。
矢作教授は同書でいくつかの症例を紹介しつつ、さらに冬山で二度にわたって起きた自分の滑落事故についても述べた。
最初の滑落事故
昭和五十四年(一九七九)三月、金沢大学医学部五年生の矢作さんは、杓子尾根から白馬岳に上がり、杓子岳、白馬槍ヶ岳、不帰嶮、唐松岳、五竜岳と踏破して、八峰キレッと小屋に宿泊。そこから鹿島槍ヶ岳、針ノ木岳、烏帽子岳、槍ヶ岳を越えて、南岳まで縦走する計画だった。
風速が四十メートルにもなると、一月分の食糧と燃料を詰め込んだ四十キロのリックサックを背負って体重が百キログラムになっても、体が浮いてしまって、バランスを崩してしまう。体感温度は風速一メートルにつき、一度C低下するので、高度三〇〇〇メートルの稜線では体感温度は氷点下七〇度Cにもなる。視界は何とか二、三〇メートルはあった。
三月二十五日、八峰キレット小屋を出発し、鹿島槍ヶ岳北峰(二八四二メートル)を登りはじめた。吹雪の中、雪庇(突風によって雪が尾根に反対側にせり出した所)と本来の尾根の境目ギリギリのところを登っていたとき、雪庇を踏み抜いて、高速度エレベーターに乗っているように、滑落し始めた。北壁は斜度六、七〇度で、六〇〇メートル下まで切れ落ちている。またたく間に止められないスピードになり、宙に放り出されては、ドッシーン、ドッシーンと雪壁に叩きつけられる。そして斜度四十五度のデブリ(雪崩によって落ちてきた氷雪ブロックが溜まっている所)を、大小さまざまな氷雪ブロックに、体が変形しそうなほど叩きつけられ、カクネ里に向って押し流されていった。
さんざん押し流された末、強烈な衝撃を受けて止まった。あたりは真っ暗で、経験したこともない力で押しつぶされている。矢作さんは必死でもがいているうちに、目の前がぱっと明るくなり、ようやく息ができた。どうやら雪崩の上に顔を出すことができたのだ。
稜線からの比高は一〇〇〇メートル、距離にして一二〇〇メートル、東京タワーを三つ縦に並べた斜面を墜ちた。助かる状況ではない。助かるはずがない。でも、全身あちこちの打撲傷と、左手首の捻挫だけで助かったのだ。
縦走を継続することしか頭になかった矢作さんは、いったん信濃大町まで出て、必需品を買い足すと、縦走を継続し、南岳から西尾根を下って、奥穂高温泉に着いた。
この滑落事故で、矢作さんのチャクラが開き、物事の本質が瞬時にわかるようになった。幽体離脱やそれに類するようなショッキングな体験をした人が、飛躍的に霊性が豊かになった人の例が数多く報告されているが、矢作さんも同じように、普遍意識につながってしまったのだ。
二度目の滑落事故
この時、矢作さんは死に直面したのだが、同年十二月二十二日、雪辱を期して、再び鹿島槍ヶ岳から南下し、針ノ木岳、蓮華岳、船窪岳を経て烏帽子岳に達し、さらに三俣蓮華岳から槍ヶ岳へ縦走するという山行に挑戦した。
しかし六日目の二十七日、針ノ木岳頂上直下の雪壁を登っていたとき、左足が滑って、とっさにピッケルで体勢を支えた。アイゼンが外れかかっている。アイゼンを装着し直して、再び雪壁に挑んだが、今度はアイゼンのジョイント部分が折れ、うつ伏せの状態で滑落し始めた。矢作さんは眼前を流れていく岩に両手で必死にしがみついた。そのまま止まらなければ、一〇〇〇メートル下の小スバリ沢まで墜ちていくばかりだ。
ようやく止まった場所は、針ノ木岳北斜面二七〇〇メートルあたり。風雪の中、数十メートル先に、北の稜線がかろうじて見える。立とうとすると、左膝に力が入らない。止まる直前、岩角で膝を打ったようだ。これでは縦走は断念せざるを得ず、左膝の痛みを泣く思いでこらえ、バスが発着する扇沢駅まで下りてきた。
バスを待つ間考えたことは、遭難しかかったことではなく、来年の三月は学生生活最後の山行になるから、これはバッチリ決めようということだけだった。そのとき、今までたどってきた岩小屋沢岳の稜線の方からこだまのような声で、「もう山には来るな~」と聞こえた。
「私はハッとしてあたりを見回したけれど、もちろん誰もいません。幻聴? いや、はっきり聴こえたんです。??? 瞬間、すべての思考が停止しました。
しばらくして、私はまるで憑き物が落ちたように、肩の力が抜けて気が楽になり、『山はもう止めた』と即断しました。これまでの執着は何だったのか。つい先までの、冬山への再挑戦に思いを巡らし、浮き立った気持ちは跡形もなく消えてしまっていました」
トレーニングも含めると、山で過ごすのは年間二百日、生活における優先順位は、①登山、②アルバイト、③学業で、大学の冬季テストは長期入山中で受けられないことが多く、翌年に下級生とともに受けていた。それほど入れ込んでいた登山を、それ以来ぷっつりやめてしまったのだ。
「あれから三十年経って、時折考えます。なぜ二度も助かったのか? あの声は何だったのか? 性懲りもなく、愚かしい行為を繰り返す私に、まだこの世でやらなければならない役割があるということだったんですね」
自分は何をするために生まれて来たのか
私は矢作教授の回想を聞いていて、佐藤一斎が『言志録』第十条に書いている条文を思いだした。自分の人生への根源的な問いかけだ。
「人は須らく自ら省察すべし。『天何の故に我が身を生み出し、我れをして果たして何の用にか供せしむる。我れ既に天物なれば、必ず天の役あり。天の役共まざれば、天の咎必ず至らん』と。省察してここに到れば、則ち我が身の苟くも生く可からざるを知らむ」
(人間は自分自身というものを真剣に考える必要がある。
「天はなぜ自分をこの世に生みだし、何の用をさせようとするのか。自分はすでに天の物であるから、必ず天から命ぜられた役目があるはずである。その天の役目をつつしんで果さなければ、必ず天罰を受ける」と。このように反省し考察すると、自分はただうかうかとこの世に生きているだけではすまされないことがわかる)
その文言を示すと、矢作教授は「その通りです。言い得て妙です」と答えた。
「人にはやるべき使命があり、それを果たすために人生という時間が与えられています。私は当初、高所医学で果たすべき役割があるのかなと思っていました。ところがどうもそれではなく、麻酔科、救急外来、集中治療室、外科、内科、手術部などに関わりました。専門医として訓練されるのではなく、多分野なことに関わりながら、新しい視点を育てられていたのです」
そして臨床医でありながら、分子生物学の研究にも携わり、医学と工学をつなぐ医療生体工学を修め、平成十一年(一九九九)、東京大学工学部精密機械工学科教授に就任した。その二年後には東京大学附属病院救急部・集中治療部部長となり、救急医学分野教授に就任する。そして翌年(平成十五年)には「コードブルー」という画期的なシステムをつくり上げるに至った。
「コードブルーとは院内で急変に気づいた人がRRT(Rapid Response Team)を呼び出す緊急コールナンバーです。出動要請がかかると、五分以内にRRTが出動し、患者さんであろうと、お見舞いの方であろうと、売店スタッフであろうと、即座に高度救命処置が行われるようになりました。毎年五十~八十件の出動要請があり、確かな成果をあげています」
その他、入退院管理センターに担当医を配置するとか、関連病院との連帯強化とか、院内危機管理体制の強化など、矢作教授がかかわった仕事は多い。
矢作教授は昔から『言志四録』を読んでおり、佐藤一斎についての論評は極めてユニークだ。
「『言志四録』は読む人が読めば、その内容が至高かつ確実なことが明らかで、佐藤一斎は神人合一していたことがわかります。神人合一という言葉は今ではあまり使われなくなりましたが、スピリチュアリストが言うところの《チャネリング》(霊人の言葉を地上人に下ろすこと)ができていた人でしょう。すごい炯眼の持ち主です」
読書とは自己との対話である
安岡正篤先生は戦前、『言志録』からしばしば引用されていた。『言志録』は人間性への深い洞察を持っており、修養には欠かせないテキストだった。しかし日本の敗戦とともに、修養に関するものは封建的として一切否定されたため、戦後はかえりみられることがなくなった。しかしながら、この本の洞察力は否定しても否定することができないので、ここでも引用した。
矢作教授は現在五十八歳ながら青年のように溌剌としており、苦労がまったく顔に出でいない。地位とか名誉欲はほとんどなく、今でも病院に寝泊まりすることが多い。登山家やヨットマンなどの冒険家には、食べることができればそれで満足という人が多いが、まったくその類いだ。
「人はシンプルな生活をすることが一番です。地球を食い尽くすような生活をいつまでも続けるべきではありません。個人の生活を省みても、食事の量を減らし、病にならない生活を心がけ、静かに瞑想するだけで、人の意識はいとも簡単に変わり、病人も激減するでしょう。
瞑想と言っても、禅僧のように大それたことをするのではなく、日々の生活の中で、自己の魂を見つめる時間をつくるだけでいいのです。自分の魂をしっかり正視すると、ごく自然に《大いなる摂理》を感じられるようになります」
《大いなる摂理》とは矢作教授の会話にしばしば出てくる用語で、佐藤一斎の言う《天》であり、村上和雄筑波大学名誉教授の《サムシング・グレート》や普遍意識を指す。
矢作教授は『言志耋録』第三条を示した。読書、瞑想について、佐藤一斎が深い叡智を示している箇所だ。
「経書を読むは即ち我が心を読むなり。認めて外物と做すこと勿れ。我が心を読むは即ち天を読むなり。認めて人心と做す勿れ」
(聖賢の書物を読むということは、即ち自分の心を読むことである。決して自分の外にある書物を読んでいると思ってはならない。自分の心を読むということは、即ち天の意図するところを読むことである。決して人の心と思ってはならない)
聖賢の書物を導きの手として、天の意図するところを探るのが読書だという。
矢作教授はもうかれこれ二十三冊の啓蒙書を書いている。その中に天皇陛下の医師団の一人として天皇陛下に日常的に接していて、天と地をつなぐ祭司であろうとして呻吟される天皇陛下の姿を垣間見て書いた『天皇』(扶桑社)がある。霊的体験を通して全体が見えるようになった矢作教授ならではの著書である。現代の覚醒者として、矢作教授の使命はますます大きくなっている。