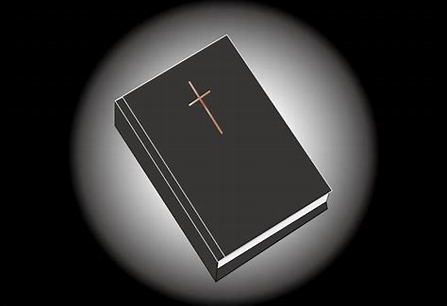「沈黙の響き その143」
キリスト教の深みを見せた『伝道の書』
神渡良平
堀田綾子(結婚後、三浦姓に)さんが前川さんに、皮相的なクリスチャンが多いと揶揄(やゆ)すると、前川さんはそれを否定しませんでした。
「表面的で、はやり病のような信者はいずれ脱落するよ。だからそんなものに目を奪われて、気持ちを腐らせるのではなく、ぼくは綾ちゃんに聖書のすごさを発見してほしいな」
そして旧約聖書の『伝道の書』を開いて読むよう薦めました。そこには、古代イスラエル王国の第三代目の王である賢者ソロモンの言葉と推測される文章が書かれていました。
「空(くう)の空、すべては空なり」
「伝道者曰く。空の空、空の空なるかな。すべて空なり。日の下に人の労して為すところのもろもろの働きは、その身に何の益かあらん。世は去り、世はきたる。地は永遠に保つなり」
その響きはまるで硬質で、人生を慨嘆(がいたん)しています。それまで綾子さんが聖書に抱いていた印象は、
「互いに愛し合いなさい」
とか、
「右の頬を打たれたら左の頬を向けなさい」
などと言った教訓的なことが書かれていると思っていました。
ところが『伝道の書』はそれらとはまったく違い、現世は虚無的だと認めた上で、そこから絶対的肯定に至ろうとしていました。
釈迦の求道も「空」から始まった
これは綾子さんにとって新鮮な驚きであり、キリスト教全体を見直すきっかけになりました。釈迦は2500年前、インドの王家に生まれ、地位と富に恵まれ、美しいヤシュダラ妃とかわいい子どもに恵まれました。一見満ち足りた状況でしたが、お年寄りに人間の衰えゆく姿を見、葬式を見て命には限りがあることを知りました。人間には避けることができない生老病死が自分の現前にも頑としてあると悩み、ついに一切を捨てて山の中に入ってしまいました。
そしてまったくの虚無感から出発したものの、釈迦はついに絶対の肯定に至ったのでした。そのことを知ったとき、綾子さんは豁然と開けてくるものがありました。そこでこう書いたのです。
〈伝道の書と言い釈迦と言い、そもそもの初めには虚無があったということに、わたしは宗教というものに共通するひとつの姿を見た。わたし自身、敗戦以来すっかり虚無的になっていたから、この発見はわたしにひとつの転機をもたらした。
虚無はこの世のすべてのものを否定するむなしい考え方であり、ついには自分自身をも否定することになるわけだが、そこまで追い詰められたときに、何かが開けるということを、伝道の書にわたしは感じた。
この伝道の書の終わりに書かれていた、
「汝の若き日に、汝の造り主を覚えよ」
の一言は、それゆえにひどくわたしの心を打った〉
三浦綾子さんはとうとう、
「自分自身を否定するところまで追い詰められたとき、何かが開ける!」
という確信をつかみました。だから『伝道の書』との出合いは、以後の堀田綾子さんの求道をまじめなものに変えました。
聖書学者の研究の成果
ところで『伝道の書』は「詩編」の後に入っている「箴言」(しんげん)同様、ソロモンは書いたとされていますが、聖書学者の間ではソロモンの著作ではなく、ギリシア哲学、特にエピクロス哲学の影響を受けて、 250~150年の間に書かれたのではないかとも言われています。
第1章14節「日の下で人が行うすべてのわざを見たが、みな空であって風を捕えるようである」の言葉が示しているように、地上的な価値や快楽は究極の安心を与えるものではなく、人間的な諸相のむなしさを伝えていて、神の思いははかりがたいと語っています。
また3章11節では、懐疑と動揺と悲観のうちに永遠を思い、神をたたえる信仰がのぞいており、 7章12節では、義人さえもが義によって滅ぶと人生のむなしさを嘆いています。その上で、人生の真相を知るには知恵が力であり、すべてを知って裁く神の前になしうることは力を尽して行為することで、神を恐れて本分を守るべきことだと力強く述べられています。
聖書学者は、本書は他の書にはみられないほど統一性を欠いているため、正典に編入されるのは遅れて2世紀ごろだったと述べています。
写真=「伝道の書」が含まれている『聖書』